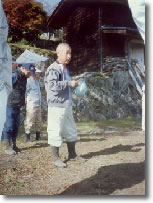![]()
2008年1月14日(月)号
![]()
<2007年11月24日・25日撮影>
 黒鍬出稼ぎ石工が積んだ坂折棚田 |
昨年11月24日(土)、25日(日)の2日間、日本の棚田百選に認定されている恵那市中野方町の「坂折棚田」において<第2回坂折棚田石積み塾」が開催され参加した。06年11月の第1回石積み塾に続いて2回目の参加である。(第1回目の模様は益田の森の川過去トップベージにて紹介) 石には8つの顔(面)があること。左右交互に積む理想的な「谷積み」は一個の石を6個か7個で包み噛み合って斜めに圧力を分散すること。横目地を通す方法の「布積み」(横積み・レンガ積み)のことや根石と天端(てんば)の構造、天端の種類など石積みの伝統工法を説明しながらその積み方をサンプル的に披露した中野方町の石積み職人の柘植功さんと実践指導に当たった同じく地元の井戸史雄さん、鷲見達夫さんの三人の石積み名人の顔を眺めていると“いい汗をかいて暮らすことの大切さ”を考えさせられる。 それにしても坂折棚田は四季折々、いつ見ても癒される。知多郡内の黒鍬(くろくわ)と呼ばれた出稼ぎ石工集団によって積まれた石積みが残る坂折棚田は地中から息づいているのだ。 今回の塾生には10代後半から20代からの女性の参加があり彼女たちのきめ細かに石を噛み合わせていく行動に触れていると元気が湧いてきた。男性となると庭師さんや石工さん、電気工事屋さんなど現役のそれぞれの世界の職人が参加し、彼らから石に関わる暮らしを教えてもらうことができた。 やはり汗を流した後の食事は今回も美味しかった。地元のご婦人の手作りによる味ご飯や漬物の数々と汁物、絶品である。坂折棚田レストランを造りメニュー提供すれば喜んでもらえること間違いない。
|
Copyright(c) 益田の森と川を育む会. All rights reserved.
「益田の森と川」の無許可転載・転用・翻訳を禁止します